

| ���̃G�b�Z�C�́A�uGARO�v�Ƃ����V�O�N�㏉���Ƀ~���[�W�b�N�V�[�����삯�������t�H�[�N���b�N�o���h�����ɁA���A���܂��Ɠy�����A���̉��y�A�F��A�����Əo��A�����ĕʂ��܂ł�Ԃ����m���t�B�N�V�����ł��B |
| written by ���܁iY. Tsuchiya�j |
| CONTENTS �N���b�N����Ƃ��̏͂ɃW�����v���܂� �o�b�N�����̃^�C�g���́uNEW UP DATE�v�ł��I |
| PROLOGUE |
| ���y�Ƃ̏o� |
| BEATLES�Ƃ̏o� |
| �M�^�[�Ƃ̏o� |
| �g�N�Ƃ̏o� |
| �f�`�q�n�Ƃ̏o� |
| �u����ۂہv�Ƃ̏o� |
| �u�Â������v�Ƃ̏o� |
| �r�N�Ƃ̏o� |
| �u�k�`�l�a(����)�v�Ƃ̏o� |
| ���芅�тƂ̏o� |
| �r.�v����Ƃ̏o� |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o��@PART-1 |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o��@PART-2 |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o��@PART-3 |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o��@PART-4 |
| �k�`�l�a�Ƃ̕ʂ�@PART-1 |
| PROLOGUE |
�f�`�q�n�ɂ��ď����Ă݂܂��H�c Tomoko.K�������炨�U���������A�˘f���Ȃ�����ƂĂ��������v���܂����B �w�����������c�H�x�@�F�X�Y�݂܂����B �����Ă��邤���ɁA�P�X�X�X�N�T���Q���́u����f�`�q�n�I�t��v�c�B �f�G�ȕ��X�ƁA�f�G�ȏo����҂��Ă��܂����B ���̌�A�l�X�Ȑl�⎖���Ƃ́u�o��v�����̐l���́A�����Ă������f�`�q�n�Ƃ̃L�[���[�h�ł��邱�ƂɁA�ӂƋC�t���܂����B �������͕s�v�c�ȏ��荇�킹�̒���Y���Ȃ���A�l�X�ȁu�o��v��ʂ��āA�l�X�Ȑl�������ł��܂��B �ŋ߂ł́A�������Ăf�`�q�n�ɂ��ď����Ă���̂��ATomoko������n�߂Ƃ���F����Ƃ́u�o��v������������ɑ��Ȃ�܂���B ���́u�o��v��ʂ��āA���Ƃf�`�q�n�Ƃ̊ւ��������Ă݂����Ǝv���܂��B ���X�����Ȃ邩���m��܂��A�������������B ���ɂȕ��́A���t��������������K���ł��B �Ȃ��A���ԓI�����W�ȂǕs���R�ȕ��������낤���Ǝv���܂����A�����ɂ��������v���o���Ȃ���A�f�ГI�ȋL���𗊂�ɏ����Ă���܂��̂ł��e�͉������܂��B�@�@�@�i�P�X�X�X�N�T���V���j |
| ���y�Ƃ̏o� |
���S���t�������特�y�ɂ͋������������i�炵���j�B �c���̍��A�Ƃɂ������d�C�~���@�Ń��R�[�h�������Ă�������A���ꂪ�ǂ�ȃW�������̉��y�ł��낤�Ƌ@�����ǂ������Ɨ��e���b���Ă��ꂽ�B ���w�Z�̍��A���y�Ƌ��H(��)�̎��Ԃ���ԍD���������B �̂��c�A�y��i�n�[���j�J�E���R�[�_�[�E�s�A�j�J�Ȃǁj�����t����c�A�ӏ܂���c�B���̂ǂ�����A���ɂƂ��đf���炵�����Ԃ������B �m���S�N�������ƋL�����Ă���B�u�g�t(���݂�)�v�Ƃ����Ȃŏ��߂ăR�[���X�ł̃n�[���j�[��̌������B �����̗]�芦�C�������B���܂�ď��߂Ă̊��o�������B |
| �r�[�g���Y�Ƃ̏o� |
|
|
| �M�^�[�Ƃ̏o� |
�@���w����B���͂�����f�r�A�O���[�v�E�T�E���Y�̐Ⓒ���B�^�C�K�[�Y�A�u���[�R���b�c�A�X�p�C�_�[�Y�A�I�b�N�X�c ���͗]�薲���ɂȂ�Ȃ������B�D���ȋȂ͐��Ȃ��������c�B  �����āA�t�H�[�N�E�u�[�������B�܂̐Ԃ����D�A���ѐM�N�A�������i�c ���ƌ����Ă��A�g�c��Y�̑��݂͑傫�������B�u�������悤��v�̑�u���[�N�B �M�^�[���~�����A�M�^�[��e����悤�ɂȂ肽���B�{�C�ŔY�B���̍��M�^�[�������Ă�����̂́A�N���X�ł��P�A�Q���������B�L���ێq�����(�H)�܂łɂ́A�܂������Ă��Ȃ������B ���̕��͂��̍��A�����w�Z�̋��@�����Ă����B�T�^�I�ȕ��e�����}���^�̌��i�ȉƒ낾�����B�r�[�g���Y��f�r�͕s�ǏW�c���Ɩ{�C�Ŏv���Ă���悤�Ȑl���������A�����������]���ꂩ���Ă����B �M�^�[���~�����Ȃ�āA�ȒP�Ɍ�����ł͂Ȃ������B ����Ȃ�����A�F�B�������Ă����G���u���}�v�i�����l�C���������|�\��j�ɍڂ��Ă��������M�^�[�E�A�J�f�~�[�Ƃ������N���b�V�b�N�E�M�^�[�̒ʐM����̐�`���ڂɗ��܂����B�u���ꂾ�I�v �����c���̍��A���̓����Ƃ��Ă͒������d��~���@�������Ă����ʂȂ̂ŁA���͉��y���D�Ƃł͂������B ���ɑ��k�������T�Ԍ�A���R�[�h�\���قǂ̋��ނƁA�N���b�V�b�N�ł͂��������A���̓M�^�[����ɓ��ꂽ�B �����Ɍ����ƁA�������̓N���b�V�b�N�E�M�^�[�ƃt�H�[�N�E�M�^�[�̋�ʂ𐳊m�ɂ͒m��Ȃ������悤�ȋC������B �Ƃɂ����A���R�[�h���Ȃ��狳�{�Ў�ɖҗ��K�����B���̍������̂��������y�ł͂Ȃ��������A�M�^�[���e����悤�ɂȂ肽����S�ŁA�N���b�V�b�N�t�@�̏������w�B���̍��̓R�[�h�Ȃ�Ēm��Ȃ������B ���T�Ԍ�A���}���X(�ւ���ꂽ�V�т̑薼�Œm���Ă���ȁB�K���̂ł͂���܂���B�O�̂��߁c)���e����悤�ɂȂ������͊����������B ���l����A�N���b�V�b�N�t�@�̏������w���Ƃ͌����Ė��ʂł͂Ȃ������̂����A���̍��́u�{�N�̂�肽�����y�Ƃ͈Ⴄ�c�v�Ƃ����v���Ă����B �F�l����R�[�h�ɂ��ċ����Ă�������̂́A����Ȏv������������������B��o�́u���}�v��u�����v�t�^�̃\���O�E�u�b�N�ɏ����Ă���`���Ƃ��b�̈Ӗ������̎��m�����B �u�D���ȋȂ��e����I�v�@���ɂƂ��ẮA�Ռ��I�������B ���ꂩ��́A�N���b�V�b�N�̋��ނ͂������̂��ŁA�R�[�h�t�@�ɂ͂܂����B �A���y�W�I�͂������A�X���[�E�t�B���K�[�t�@���ł���悤�ɂȂ����B �����ł͌��\�I�����肾�����̂����c�B |
| �g�N�Ƃ̏o� |
 �@���u�]�̌������Z�Ɏ��s�������́A�s�{�ӂȂ��玄���̇T�w�����Z�Ƃ����j�q�Z�ɓ��w�����B �@���u�]�̌������Z�Ɏ��s�������́A�s�{�ӂȂ��玄���̇T�w�����Z�Ƃ����j�q�Z�ɓ��w�����B���̔N�̉āA�K���Ƀo�C�g���āA��������L���������_�c�̃J���Z�y��Łu�r���[�v�Ƃ����I���W�i���M�^�[����ɓ���Ă����B�m���V���~�ʂ������Ǝv�����A�����̍��Z���ɂƂ��Ă͂��ꂱ���啱���������B ���̍��e���Ă����̂́A�g�c��Y�A�������ƘZ���K�A���܂�Ђ낵�A������BEATLES���ł������B ���̍��Z�ɂ͕t���̒��w�Z������A��������オ���Ă������k�̒��ɂg�N�������B �ނ͌y���y���D��i�����Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ������j�ɏ������Ă���A���X�A�w�Z�ɃM�^�[������Ă���ė��Ă����B �g�N�̓M�^�[���I���ƁA�N���X�Ő��̕]���������B ���ۂɔނ̃v���[�������Ƃ͂Ȃ��������A����Ȕނ����͂����������Ɉӎ����Ă����B ���w�㔼�N�ȏ�o����������A�v�����|�����ނ���b��������ꂽ�B �u�s�N(���̖�)���M�^�[�e�����āH�v ���ꂵ�������B�b���Ă݂āA���R�o���̉Ƃ��߂��ł��邱�Ƃ����������B�������̏T���ɔނ̉ƂɗV�тɍs���������B ���Z�P�N���̔ӏH�������B �m�����̂X���O�ɂ͔ނ̉Ƃɒ������悤�Ɏv���B �]�k�����A���̓����͓������疭�ɒ��������������̂������B ���������A�w�I���A�I���ƕ]�������A�I���̃e�N�ŕԂ蓢���ɂ��Ă��I�x�ʂ̂��Ƃ��l���Ȃ���ނ̉Ƃւƌ��������悤�ȋC������B �g�N�͂����ނ�ɃM�^�[�����o���ƁA���ꂽ����Ńn�[���j�N�X�E�`���[�j���O���n�߂��B����ȑO�ɁA���̓n�[���j�N�X�E�`���[�j���O���o����F�l�ɉ�������Ƃ͂Ȃ������B �w�����A�ł���I�x���͒��������B ���̌�A��l�ʼn���e�������낤�c�H �͂�����o���Ă���̂́A���܂�Ђ낵�́u�l�t�̃N���[�o�[�v�Ə���P�F�ƘZ���K�́u�o��(���т���)�̎��v�ʂ����A�͂����茾���Ĕނ͍I�������B�����̎��ȂǁA�����ɂ��y�Ȃ������B �u�l�t�c�v�̃C���g���̃��[�h���܂�܃��R�[�h�ʂ�A�ނ͒e�����B�����̒t�ق����p�������������B �������ނ̓V���b�N���Ă��鎄�ɁA���������Ă��ꂽ�B �u�s�N�āA�S�I���ˁI�v(��) ��l�̃��p�[�g���[����i�����������A�ނ������������B �u�s�N�A�K�����Ēm���Ă�H�v |
| �f�`�q�n�Ƃ̏o� |
�@���̖��O�͕��������Ƃ��������B�m���t�@�[�X�g�E�A���o������������Ă���قǎ��Ԃ��o���Ă��Ȃ����������Ǝv���B�������A���͎����Ă��Ȃ������B �u���O�͒m���Ă邯�ǁc�B�v �������������ɁA�ނ� �u������ƒ����Ă݂Ȃ��H�v �ƌ����āA���͊K���̕����Ɉē����ꂽ�B ���̕����ɒʂ���Ď��͋������B�����I�[�f�B�I�@��̐��X���I �u�Z�M�̂Ȃc�v �ނ͏Ƃꂭ�������Ɍ������B �����́A�����ł͒��������S�ȃI�[�f�B�I��p�̕����ŁA�Q�g���b�N�R�W�̃I�[�v�����[���E�f�b�L��A�������Ȃ��قǂ̂k�o���R�[�h������ł����B �ނ��A���̒�����P���̃��R�[�h�����o�����B �u����Ȃ��ǁc�v  ���̃��R�[�h�̃W���P�b�g�ɂ́A���ۂ��ʐ^�̒����Ńx���{�g���̃W�[���Y���͂����R�l���ʂ��Ă����B�Œ��ꒃ�i�D�ǂ������B ���̃��R�[�h�̃W���P�b�g�ɂ́A���ۂ��ʐ^�̒����Ńx���{�g���̃W�[���Y���͂����R�l���ʂ��Ă����B�Œ��ꒃ�i�D�ǂ������B�u���ꂪ�K�����c�v���́A�����̉^���I�ȗ\���������B �ނ͒��Ӑ[���J�[�g���b�W�̐j���A�^�[���e�[�u���̏�ʼn�]���Ă��郌�R�[�h�ɗ��Ƃ����B ���܂Œ��������Ƃ̂Ȃ����̑剹�ʂŁA�u��l�ōs�����v�̃C���g�����n�܂����B ���̎��̊��o�A������ǂ��\�������炢���̂��낤�c�B �X�s�[�J�[�̃E�[�n�[����o�X�h�����X��A�g�D�C�[�^�[����M�^�[�����߂����������A�X�R�[�J�[����͈ꎅ����ʔނ�̃n�[���j�[���ڑO�ɔ�яo���Ă����B ���w���̎��Ɋ��������́u���C�v�̍ŋ��ł������P�����B �����g�N�����ɂ��Ȃ�������A���͐����グ�ċ����Ă��������m��Ȃ��B ���̎��A�K���Ǝ������͕�����Ȃ����������ɑ��݂����I �k�o�ꖇ�����I���̂�����ȂɒZ���������o���́A���̐l���Ō�ɂ���ɂ����̎���x���肾�B �Ō�́u�l�͐��܂�āv���I�������A���炭��R�Ƃ��Ă��܂����B �u����A�ꏏ�ɂ���Ă݂Ȃ��H�v �g�N�����������Ɍ������B�f�闝�R�ȂǁA����͂����Ȃ������c�B |
| �u����ۂہv�Ƃ̏o� |
�@�u����A��낤�I��낤��I�I�v �����g�N�Ɠ��������l���Ă����B�ނƈꏏ�ɂ�肽�������B���̔ނ���̗U����f��͂����Ȃ������B �ނ�����U���Ă��ꂽ�c�B�ނ�����F�߂Ă��ꂽ�c�B �{���Ɋ����������B �ŏ��ɉ�����낤���ƁA�b���������o���͂Ȃ��B�ǂ��炩�Ƃ������A�u����ۂہv����邱�ƂɂȂ����B 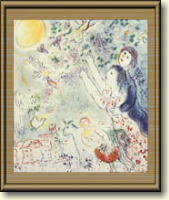 ���̃}�[�N�̑�����������������A�ɒ[�Ƀ}�C�N���I���ɂ����^���c ���̃}�[�N�̑�����������������A�ɒ[�Ƀ}�C�N���I���ɂ����^���c�U���̑傫���r�u���[�g�c �s�v�c�Ȑ����̃��[�h�E�M�^�[�c ���̒��̐��E��Y���悤�ȃn�[���j�[�c �n�C�|�W�V�����R�[�h�`�F���W�̎��̍���Ō����C�鉹�c �����������V�N�������B�����āA�����������Ռ��������B ���̍����狻������������D���ȉ�Ƃ̈�l�A�}���N�E�V���K�[���̐��E���Ǝv�����B �����A�u����ۂہv�͂���Ȃ�ɔ���Ă��āA��o�̌|�\���ʍ��\���O�u�b�N�ɃR�[�h�i�s�����͍ڂ��Ă����B �c���Ŏn�܂�V���v���ȃC���g���c �ł��������̒m���Ă���c���Ƃ͈Ⴄ���̂悤�ȋC�������B �u�����Ⴄ��ˁH�v ���������ƁA�ނ����Ȃ������B �u�������ˁc�n�C�R�[�h���ȁH�v ��܃t���b�g���c�̃n�C�R�[�h�Ŏ������B�ł��������肱�Ȃ��c�B ������x���R�[�h�������c���Ղ����Ղ��������B ��Ɉꌷ�̂`�̉��������Ă���c�B�ł��n�C�R�[�h����Ȃ��c�B �ӂƁA�����Ƀ��[�R�[�h�ɉ����A���w�ňꌷ�̑�܃t���b�g(�`)���������Ă݂��B �u�W�����`���v(�I)�@���A���ꂾ�I�I �u���ꂾ��I�I�v�g�N�͋��I ���v���ΒP���Ȃ��Ƃ����m��Ȃ��B�ł������̎������ɂƂ��āA����͉���I�ȑ����������B�������́A�������ň�t�������B ���̌�A�K���̃R�s�[�͂g�N���������������A�����𖾂���Ƃ����������S�����m�ɂȂ����B �C���g�����o����Ό�͑��������B ���R�ƃ��[�h�{�[�J���͎����Ƃ����B ���́A�}�[�N�̐����o�����������B����A�}�[�N�ɂȂ肽�������B �@�ׂŁA�D�����āA����ł��Ēg�������c �ꐶ�����A�ނ̉̐����Č����悤�Ƃ����B�������܂��܂��������B���A�ނ��� �u�}�[�N�Ɏ��Ă��I�v �ƌ���ꂽ���ɂ́A�{���Ɋ����������B �ނ̓M�^�[�̃��[�h��e�����B�������ƂɁA�ނ̓��R�[�h�𐔉��������ŁA����Ɩw�Ǔ����t���[�Y�Ń��[�h��e�����B �T�r�̕������A����������u�����C�鉹�v�𗊂�ɁA���[�|�W�V�����R�[�h�łȂ����Ƃ͕������Ă����B���̂������Ńn�C�|�W�V�����œ��������o���̂ɁA��������Ԃ͊|����Ȃ������B�������łȂ��A���́u�����C�鉹�v�����ʂƂ��ďo�����Ƃ����ӎ��ł����B �����āA�u�����A�����A�����A���[�c�v�̃R�[���X�B �R�[���X�́A���ɂƂ��ē��ʂɑ�Ȃ��̂������B �g�N�Ǝ��̐��́A���̎����S���Ⴄ�ɂ��ւ�炸�A���ꂢ�ȃn�[���j�[���Y�B ���x���J��Ԃ������ɂ���炵���͂Ȃ����B���A���R�[�h�Ƃ͑S�R�Ⴄ�B �����c �u������l�A�����o�[���ق����ˁB�v �ǂ��炩��Ƃ��Ȃ��A�ꂢ�Ă����B �������A�������̃o���h�ɁA������l�̃����o�[�������܂ł́A�㐔�����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �ނ̕�ォ��̌Ăѐ��ŋC���t������A������̂X��������Ă����B �H������炸�ɂP�O���Ԉȏ�A�f�`�q�n�̐��E�ɐZ���Ă����̂��B���čK���Ȑ��E�������̂��낤�I �y���������o�̂͑������A����ȂɒZ���P�O���Ԃ��o�������̂����߂Ă������B �����̕��ی�̍ĊJ����ċA�H�ɂ����B ���]�Ԃ̃L�����A�ɃM�^�[��t���āA�u����ۂہv���̂��Ȃ���铹�𑖂����B �������ӏH�̖镗���ΏƂ����̂ɐS�n�悭�����Ȃ���A���͊m�M���Ă����B �w�����V�������E���n�܂����x�Ɓc |
| �u�Â������v�Ƃ̏o� |
�@��������ꂸ�Ɍ����ƁA�J���I�P�̑啁�y�̌��߂��A���݂̂悤�Ɂu�ꉭ���̎�v�̎���Ƃ͈Ⴂ�A�����͉̂��I���F�l��{���̂́A��ς������悤�ȋC������B �M�^�[�����t�ł���K�v�͂Ȃ��������A�̂��I���A����ɉ��������钇�Ԃ��~���������B ���̑{���́A������ɂ߂��B���̊Ԃ��A��l�łقƂ�ǖ����̂悤�ɗ��K�����B �u����ۂہv�̃R�s�[�͈�T�Ԓ��Œቹ�R�[���X�p�[�g�������A�قڊ��������̋Ȃ͉��ɂ��邩�b���������B �g�N�ƈꏏ�ɂf�`�q�n����邱�ƂɂȂ������̓��ɑ����u�f�`�q�n�P�v����ɓ���A��l�̎��ԂɎC�茸��قǒ����Ă������́A�u�Â������v���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ������B  �s�v�c�ȋ����̃M�^�[�P�{�̃C���g���c �̂��o�����甚������n�[���j�[�c �g�Ȍ`���̋Ȃ̍\���c �˔@���͋C����ς���}�[�N�̃\���c �������n�[���j�N�X�̊ԑt�c ���̍�����}�X�����������́A�u�Â���������낤��I�v�ƁA�咣�����B �ނ́A�u���`��A�{�N���D���Ȃ��ǂˁc�v�ƁA�˘f���Ȃ���A �u�`���[�j���O���Ⴄ�炵���c�v �ƍ������悤�Ɍ������B �����Ȏ��ɂ́A�ŏ��Ӗ���������Ȃ������B ���̎��܂ŁA�M�^�[�̃`���[�j���O�͗B�ꂾ�Ǝv���Ă����B����Ȏ��́A�N���b�V�b�N�M�^�[�̋����{�ɂ͏����ĂȂ������B �u�ǂ��������ƁA����H�v ��������炸�A�q�˂鎄�ɁA�ނ́A �u�ϑ��`���[�j���O���Č����炵�����ǁc�v�ƙꂭ�悤�Ɍ����ƁA�U�������ߎn�߂��B �u�H�H�H�v�ƕs�v�c�����ɂ������߂鎄�c �U�����c�Ƀ`���[�j���O�����ނ́A���ʂɂc���̃��[�R�[�h�Łu���炟�[���`�������Ł`�v�Ɖ̂��n�߂��� �u�ˁA�������Ⴄ����H�v�Ǝ��������B ���́A�m���ɈႤ���Nj����͎��Ă�Ǝv�����B �u���R�[�h�A�����Č��悤��I�v �������́A��̃I�[�f�B�I���[���ɃM�^�[���������B ���̍��́A���̂悤�Ɂu���S�X�R�A�v�Ȃ�ē���s�\�������B���܂ɁA�u�K�b�c�v��u�����O�M�^�[�v���̃M�^�[�G���ŁA�Z�����W���g�܂����x�������B�������A�����������̃R�s�[�ɒ��킵�Ă���i�K�ł́A�܂��R�s�[�X�R�A�Ȃ��������B �������́A���Ղ��J��Ԃ��u�Â������v�����B �m���a�ʂ̂P�Ȗڂ������̂ŁA�܂��y���������A�A�i���O�J�[�g���b�W�̐j���グ�Ă͉�����Ƃ���������J��Ԃ��̂͑�ςȂ��Ƃ������B���Ȃ�u���s�[�g�v�̃{�^��������c�B �c�ӂƁA�o�����̂U������P���ɍ~��Ă����Ƃ��낪�C�ɂȂ����B(�I) �u�g����i�����ނ����̂ŌĂԂقǒ��ǂ��Ȃ��Ă����j�I�C���g���̎n�߁A�J��Ԃ��āI�v �u���A�������I�I�v �ނ������l�������Ƃ������ɕ��������悤�������B �}���Ń��R�[�h�ʂ�̉��ɁA�J�������`���[�j���O�����B �u�˂��A����ł�����Ȃ��H�I�v ���̃C���g���́A�}�[�N�����ꂽ�A�������ւ̏d��q���g�������̂��I ���́A�����Ɋm�M�����B�Ȃ��Ȃ�A���w����ɒe�����u�ւ���ꂽ�V�сv�̂悤�ɁA�ꌷ�����Ń����f�B�[�����A��͖w�NJJ�����̃A���y�W�I�t�@�Ń��R�[�h�Ɠ����C���g�����e�����̂�����c�I�I �@���́A��̂X���߂��ɔނ̉Ƃ��玩��ɓd�b����ꂽ�B �u�����͂g�N�̉Ƃɔ��܂邩��c�v �d�b�̌������ł́A��e���s�@�������Ɍ������B �u�����������͑O�����āA�����ƒf���Ă���ɂ��Ȃ����I�����d�b���āc�I�v ����Ȏ����������āA����ȓ��ɋA�����̂�(�I)�A�Ǝv�������A��e�ɘb���Ă��n�܂�Ȃ��B ���̓��͎��̐l���ŁA���߂ėF�B�̉ƂɁA���������㏳���Ŕ��܂������ɂȂ����B �����Ƃ����܂����Ƃ͌����Ă��A�ꐇ�����Ȃ��������c�B ���̓��A�O��Łu�Â������v��ȑS�āA��������������Γ����R�[�h�ɂȂ邩��l�ʼn𖾂����B �}�[�N�̃T�r�̕����ł͈�ԋ�J�����B�ϒ�����̂ŐV�����|�W�V������T���Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B�������A���̕�������Ԃ̎��̒������ǂ���Ȃ̂ŁA�����ƕK���ɂȂ����B �ԑt�̃n�[���j�N�X�͂g�N�������ɃR�s�[�����B�ނ̓M�^�[�̂Ђ�߂����f���炵�������B �R�[���X�̃p�[�g�́A�����𖾂����B�n�[���j�[��T���̂����͎��M���������B ����������Ԃ��u�Â������v��Ȃ����A���s���Ă͍ŏ�����A�J��Ԃ����K�����B �v���Ζ钆�ɁA������I�[�f�B�I���[���̒��Ƃ͌����A�M�^�[�������炵�A�吺�Łu�g�D�������A�g�D�A�g�D�A�g�D�A�g�D���I�c�v�Ƃ���Ă���̂�����A�ނ̂����e���悭�䖝���Ă��ꂽ�Ǝv���B �[���ł��鉉�t���ł������ɂ́A�������~�̖邪���X�Ɩ����Ă����B |
| �r�N�Ƃ̏o� |
�@���B�́A�����Ƀ��p�[�g���[�𑝂₵�Ă������B ��o�̂Q�Ȃɉ����u��l�ōs�����v�u�n���̓����[�S�[�����h�v�u�Ԃ̓`���v�u�����ȗ��v�c �������Ă�Ԃɓ�l���ꂼ��̃p�[�g���A���͂����肵���B �g�N�̓g�~�[�A���̓}�[�N�̃p�[�g���̂��A���t����B �������A��l���ڎw���u�f�`�q�n�̊��S�R�s�[�v�ׂ̈ɂ́A��Ƀ{�[�J���̃p�[�g���̂��郁���o�[���K�v�������B ���p�[�g���[�𑝂₷���Ԃɂ��A���l���̗F�B�ɂ���ƂȂ��b���A���̂����̉��l���Ƃ́A���ۂɉ�킹�Ă݂�����������c �̂��I�����c�͊F���������B �����������Ă���Ԃɔ��N�߂����Ԃ��߂������Ă��܂����B ��l�ł�邩�A�Ë����Ă��������̃��c�Ƒg�ނ����Ȃ��̂��c ���Β��߂������������A�g�N�̗F�B��ʂ��Ăr�N���Љ�ꂽ�̂́A�����V�w�N�ɓ������m���T�����������B ���g�Ń��C���h�Ȋ����̊O�ςƂ͗����ɁA���₩�Șb���������郄�c�������B �u�K������Ă���ĂˁB�{�N���D���ȂB�M�^�[�͑S�R�e���Ȃ����ǁc�v �������̓��̕��ی�ɁA�g�N�̎���ɎO�l���W�������B ���������āA�����g�N����������҂��Ă��Ȃ������B���܂ʼn��Ղ����҂𗠐��ė������A�ň���l�ł��ꂩ�������Ă������Ƙb�������Ă������������B �Öق̂����̂��́u�I�[�f�B�V�����v�́A�����̂悤�Ɂu�Â������v�ł�邱�Ƃɂ����B �u�r�N�A�Â������̃{�[�J���̃p�[�g�̂���H�v �q�˂鎄�ɁA�ނ́A �u�����Ă����Ή��Ƃ��c�v�ƁA�������B �����A�����������B ���܂ŁA���l����������āA���Ոꐶ���������Ă���Ă��A�����Ɏ�����ɒނ��đS�R�Ⴄ�����f�B�[���̂��o���B �����āA��̕�����Ȃ��Ƃ�����ׂȂ���A��̕�����Ȃ������������B �ŁA���̂����O���ă`���[�j���O�̋������M�^�[�Ŏ����̍D���ȗz���́u�����ցv���Ȃ̂��o���B �M�^�[���e���Ȃ��ނ͂��̐S�z�͂Ȃ����ǁA�ǂ����ނ����ނȂB �����Ƃ������B ���́A���Ύ����I�ɔނ̃p�[�g�A�܂�{�[�J���̃p�[�g���̂����B �ނ������̗F�B�ƈ�����̂́A���|�I�Ȕނ̐^�����������B �ނ͎��̉̂�K���ɒ����Ă����B�����āA������u�S�����A�������I�v�Ǝ��Ƀ��N�G�X�g�����B �ނ̐^�����Ɉ������܂�Ď������x���̂����B����ڂ���ނ����ƈꏏ�ɉ̂��n�߂��B �u(�I)�I���I���������������Ă���I�����A�����邩���I�I�v ���x���J��Ԃ������ɁA�ނ͏��X�Ɏ����̃p�[�g�����̂ɂ����悤�������B �u���Ⴀ�A���낻�덇�킹�Ă݂悤���H�v�@�g�N�������������v����Č������B �C���g���͏ȗ����āA�̂��o���̎l���ߑO����n�߂��B �u���炟�[���`�������Ł[�A�ӂ����[���`�股�͖ق�[�c�v ���ꂾ�I�I�@�l�������߂Ă��̂́A���̃n�[���j�[���I�I �r�N�͖ڂ���Ȃ���A�K���ɉ̂��Ă����B ���͂g�N�Ɩڂ������A�̂��Ȃ���݂��������������B ��̊��C�̘A�����A�����P���Ă����B �������āA�����Ċy�����Ď��͉̂��Ă�r���ŏ��o���A���ꂪ�~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����c �u�S�����A�S�����I�����āA�������́c�v�@���t�𒆒f������b�����ɂ��Ă����l�ɑ��A���������̂�����Ƃ������B �V�����o���h���悤�₭�a�������u�Ԃ������I |
| �k�`�l�a�i�����j�v�Ƃ̏o� |
�@�r�N���u���@�v���āA����ƂR�l�g�ɂȂ����������́A���܂ł̂Q�l�̃��p�[�g���[�ɔނ̃p�[�g�������邽�߁A���Ԃ�������Η��K�ɗ��K���d�˂��B �����������鍶��́A�C��ăt���b�g�����ʼn����Ă��܂����B�w�������A���ꂪ��������ƃJ�`�J�`�ɂȂ����B �̂������āA�A���ɂ��Ȃ�̂����풃�ю��ɂȂ����B �v���A�������̃o���h�ɂƂ��Ĉ�ԏ[�����Ă������������������m��Ȃ��B �V�����Ȃ̐������A�V�����������҂��Ă����B �u�����y���ށv�c�@���y�̌��t�̈Ӗ���{���Ɏ����ł��������������B ���T�Ԃ��āA������x�o���h�Ƃ��ẴT�E���h�������Ă������A�N����Ƃ��Ȃ��b���o���B �u�݂�Ȃɒ����������ˁc�v �����A�l�O�ʼn��t����@��Ƃ����A�u�����Ձv���u�\�S��v�ʂ��炢�������������B ���ł͒��w�����������������Ń��C�u�n�E�X�����A���������̉��t�\���Ă��邪�A�����͂���Ȏ����l���鎖����o���Ȃ������B �u�����Ղ܂ł��ƂT�������c�v ������̘b���Ǝv�����B �u���̂ˁc�v �g�N�������̂悤�ɁA���������ɐ�o�����B �u�y���i�y���y���D��j�̒���R���T�[�g���V���ɂ�����ǁc�v �����������B �ނ́A��Ȃ��Ƃ�������Ō����B ����ȑ厖�Ȏ��A�����Ƒ��������Ă����Θb�͑����̂Ɂc�I �u���ꂾ��A����I�I�v �u�ł��ˁA�y���ɓ������Ȃ��Ɓc�v �u�������Ă邳�A����Ȏ��I���œ������邳�I�I�v �g�N�Ƙb�����͂�������Ȋ����������B�������e���|����������Ă���ނ��A�M�^�[����������Ɛ��m�ŁA�������C�}�W�l�[�V��������v���C������̂��s�v�c�Ŏd�����Ȃ������B �������́A�����ɂł��y���y���D��̓����\�����݂����悤�ƌ��߂��B ���̂��߂ɂ́A�o�^����o���h�����K�v�������B ����́A�{���Ɋy�������Ԃ������B�݂�ȁA����Ȃ��Ƃ����������A�������ɂ��Ȃ邭�炢�ɏ����B �u�x�i���̖��j�Ƃ��̒��ԁc�v�Ƃg�N�B ������A����I�����Ƃ��i�D�ǂ��Ȃ���I �u�g�A�s���r�c�v�Ƃr�N�B �o����`�B�u�b�A�r�A�m���x�v�̂���p�N������Ȃ����I �u���K�I�v�ƃo�J�Ȏ��c�B ���߂��`�I�^�ʖڂɂ���`�I�I �������u���K�v�͑����ɋp�����ꂽ���A�f�`�q�n�ɂ��ȂO���[�v����t�������Ƃ͎v�����B �N�����u����ۂہI�v�ƌ������B  �u���`��A���������̎q�̃t�H�[�N�O���[�v�݂�������Ȃ��H�v �ł��A����ۂۂ��c�B���́A����ۂۂ̉̎���z���o���Ă����B �w�u�����͋���сA�̐X�ցc�x �����A�u�o�[�h�v�c�A���܂������Ȃ��B�̐X�c�u�O���[���E�E�b�Y�v�c�A�S���t�ꂩ��I�@ �w�r�͋u���z���A��͂����܂���x �r�H�A�u�V�[�v�v���c�A����Ȃ���u�}�g���v�H�ʖڂ��A�����I �҂Ă�A�r���āc�A�q�r�̂��Ɖp��ʼn��Č�����H �u�g����A�a�p�݂��āI�v ���͋}���Ŏ����ׂ��B�����ɂ́y���������z�Ə����Ă������B �u�����u�`�H�v�܂��g�N���c(�I) �u�Ⴄ��A�����I�����L�����Ă�ˁI���͔������Ȃ��́I�I�����������ƈꏏ�I�v �u�Ӂ`��A�����ˁ`�A�����u�A�����u�c�v�Ƃ܂�����g�N�B������L�~�́c�A�u�u�v��t���Ȃ��I�I �u����A������Ȃ��I�I�v�Ƃr�N�������Ă��ꂽ�B���̎��قǂr�N�������������������Ƃ͖����B �����ɏ����s�������Ȃg�N�͂ق��Ƃ��āA�O���[�v���́u�k�`�l�a�v�Ɍ��肵���I |
| ���芅�тƂ̏o� |
|
|
| �r.W����Ƃ̏o� |
�@�y������R���T�[�g�̌�A�������͊w�Z���ł�����Ƃ����L���l�ɂȂ��Ă����B �������A�u�����ςȂɑ����������R�~�b�N�o���h�v�Ƃ����\���Ȃ��͂Ȃ��������A�u���͔h�̂f�`�q�n�R�s�[�o���h�v�Ƃ����]�������������B ���܂Řb�������Ƃ��Ȃ����������y����ˑR�b��������ꂽ��������B�����̐l�ɔF�߂�ꂽ���Ƃ��A�����������B �������́A���̌�����K���d�˂��B �����āA�H�̕����Ձc�B �������uLAMB�v�͌y���y���D��̃��C���X�e�[�W�Ƃ͕ʂɁA���D����F�̐�p�������l�����邱�Ƃ��o�����B �Ƃ͌����Ă������������������m���������A����͉���I�Ȃ��Ƃ������B �����͓y�j���ɂ�������炸�A�����̋q���w�Z��K��Ă����B ���̊w�Z�͐�ɏq�ׂ��悤�ɒj�q�Z�ł������B���i�͉��������Ă���Y����̏W�c���B �������A�����Ղ̊��Ԃ����͏��̎q�̐����j�q�����|����B(�I) ���ӂɂ͂R�̏��q�Z������A���͂ǂ������m��Ȃ����A�������̍��Z�́A���ӂ̏����k�̊Ԃł��Ȃ�l�C���������B ���̋����ɒu���ꂽ�֎q�͂R�O�Ȃ��炢�������낤���c�B �������̃t�@�[�X�g�X�e�[�W���n�܂�O�́A�P�O�Ȃ��炢�������܂��Ă��Ȃ������B �����Ղʼn��t�����Ȃ�A�L����ƁA�u�Â������v�u����ۂہv�u��l�ōs�����v�u���������āv�u�����ȗ��v�u�l�t�̃N���[�o�[�v�u�Ԃ̓`���v�u�n���̓����[�S�[�����h�v�u���Ԃ͉S�����ǁv�u�w���X�̋i���X�v�i�r�N�̋����v�]�Łc�j�Ȃǂł������B �m���P�Ȗڂ́u�Â������v��������悤�ȋC������B �u���̃X�e�[�W�Ƃ͈Ⴂ�A���O�Ɩw�Ǔ��������ł���_�A���قǒ��O�̐��������Ȃ��_�A��x�C����������蔲���Ă���_�Ȃǂ��炩�A�w�Njْ������L���͂Ȃ��B �C���g���̌�A�R�[���X���̂��o������������I �債�Đ�`�����Ȃ������ɂ�������炸�A�������̉̂�L���Œ����ė����̂��A�ǂ�ǂ�A�ǂ�ǂO�������Ă����I�I������w�Ǐ��̎q���I�I �A�b�Ƃ����ԂɐȂ͂����ς��ɂȂ�A�����������肫��Ȃ��Ȃ�A�L���ɂ܂ŗo�����B(�I) �u���������āv�ł����Ẵ��R�[�_�[�̉����Ђ�����Ԃ����Ƃ��Ȃ������B ��ȁA��Ȃ̒��O�̔��������������I�@�������́A��X�^�[�ɂȂ����悤�ȋC�������B ����ڂ͂��ꂱ���A�A�b�Ƃ����ԂɏI������B �����ē���ځc ���̊w�Z�ł́A�ޏ������鐶�k�B�̖w�ǂ���o�̎��ӂR�Z�̏��q�ƕt�������Ă������A�g�N�͂ǂ��łǂ��m�荇�����̂��A�����ɂ���~�b�V�����n���q�Z�A�i�r�w�@�̐��k�ƕt�������Ă����B ��b�̃e���|�͒x�������ɁA�����������Ƃ����͂������肵�Ă��郄�c���B �������ɂ̓K�[���t�����h�ƌĂׂ�悤�Ȏq�͂��Ȃ������B���w����ɍD���������d����ɑ̂悭�U���āA�P�N���߂��悤�Ƃ��Ă����B �u���̂˂s�N�A�{�N�̔ޏ����F�B�A��ė�����Ă��I�I�v �g�N���A�����ˑR�����������B �܂������I�@�����Ƒ��������悧�`�I�@���͂ǂ������������ǁA���^�Ƃ������ƋC���g�����̂Ɂc�I�I �Ƃ͎v�������A�g�N�̂��̃y�[�X�ɂ͊�������ɂȂ��Ă������A�債�Ċ��҂����Ă��Ȃ������B ����́A�ߌ��Ԃ̃X�e�[�W�������Ǝv���B ���̎����́u���������āv���̂��Ă����B �g�N���ޏ��̂��߂ɋĂ������R�́u�\��ȁv�ɔޏ������͂����������ė����B �̂��Ȃ���A�R�l�̈�Ԍ�납������ė������̎q�Ɏ��͓B�t���ɂȂ��Ă��܂����B �������Ⴍ�āA�F���ŁA���̒������̎q�������B ���ڂ����̓����傫���A�炪�����ȏ��̎q�������B �D�������ŁA���ƂȂ������ȏ��̎q�������B ���͖ڂ��Ԃ��ĉ̂����B�łȂ��ƁA�ӎ��������Ă��܂���������������c�B �̂��Ȃ���A�܂����̊��C������ė����B ����͍��܂łƈႢ�A�傫���ۓ���ł����Ȃ��玄�̑̂��Ă������B ���̎q�̖��O�́A�r.�v����Ƃ������B �ޏ��̂��Ƃ����͈ꐶ�Y��Ȃ��c |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o� PART-1 |
�@�r�����c �����̂悤�ɔޏ��̖��O���ĂԂƁA���ł������ɂށc �����Ղ̌�A���ȏЉ���o���Ȃ������B ���O����q�˂��Ȃ������B �����Ղ͂T���߂��ɏI����āA�������ɂ͌�Еt�����c����Ă����B �ޏ������݂͂�ȓ����s�ɏZ�܂������������߁A�������̍Ō�̎d�����I���̂�҂��Ă��鎞�ԓI�]�T�͂Ȃ������B �W���܂łƂ���������������������̂��B �������Ȃ��قǂ�������ƁA�ޏ������͋A���Ă��܂����B �ޏ��������A������A�g�N���j�R�j�R���Ȃ��玄�ɐq�˂��B �u�ǂ��������`�H�v �u����A���̂�������Ȕ��̒����q�A���������c�v �u�r�q�������Ă������āc�v �u�r�q�����c�v �u�ǂ����那�`�H�v �ǂ����������������A�����ȒP�ɍs�����̂��I �t�Ɂu�ǂ���������́H�v�ƕ����������炢���I �ق��Ă��鎄�ɂg�N�́A �u���T�A�ޏ������̂i�r�w�@�̕����ՂȂ��āI�v �܂��L�~�́`�I�@�����Ƒ����v�_��b���Ă����I �u�łˁA�ꏏ�ɍs���H�v �u�s���A�s���A�s����I�I�v ���ꂩ��ƌ������́A���̐S�̒�����r������Ȃ��Ȃ����B ����Ȋ���́A���߂Ă������B ����Ȏ��ɂƂ��āA�g�N�͉��y�̒��Ԉȏ�ɁA�Œ��ꒃ��ȃL�[�E�p�[�\���ɂȂ����B �����Ĕނ����ޏ��Ƃ̋��n�����͂��Ȃ��̂�����c ���X����Ȃ��L���[�s�b�h�ł��������A���̍��ґ�͌����Ă��Ȃ��B ���ł��ǂ��B���ł��ǂ�����A�r����̏�~���������B ���̌�A�g�N�Ɣނ̔ޏ��͓d�b�ŘA������荇���A���̋C������ޏ��ɓ`���Ă��ꂽ�炵���B ������A�g�N����u���܂��s��������`�v�Ɓu�g��v��������B �]�k�ɂȂ邪�A���Ȃ瑦�A�d�b�ő���ƒ��ڃR���^�N�g�����A�f�[�g�̐\�����݂����āc �ƂȂ�̂��낤���A�����̏��Ȃ��Ƃ��������́A����Ȏ��ƂĂ��o���Ȃ������B �����̓����ɂ���i�r�w�@�̕����Ղɂ͌ߑO�P�O�����ɂ͒��������낤���B ���q�Z�ɓ���c�A�������r����ɍĉ�ł���@��Ǝv���Ɩ{���ɋْ������B ��t�ŏ��Ҍ��i�g�N���ނ̔ޏ��������Ă����B���ɏЉ�҂̖��O�������Ă���B�j���o���ƁA���炭���Ăg�N�̔ޏ��Ƃr���������̑O�Ɍ��ꂽ�B ���̑O�̎����̎��ȏ�ɁA�Z�[���[���̂r����ῂ��������B �ޏ������́u�}�W�b�N������v�Ƃ������T�[�N���ɏ������Ă���A�ŏ��ɂ��̃u�[�X�Ɉē����ꂽ�B ���R�Ƃg�N�͔ނ̔ޏ��ƁA���͂r����ƈꏏ�ɍs�������B �����Ղ̊J���I�ȕ��͋C����`���Ă��A���Ƃr����͐F�X�Ƙb�����Ƃ��o�����B �ޏ��͎��ɃJ�[�h�E�}�W�b�N���I���Ă��ꂽ�B �u�܂�����Ȃ́c�v�ƌ����Ȃ���A�����Ȏ�ňꐶ�����J�[�h���V���b�t������ޏ������炵�������B �Ă̒�A���s���āu���A�ԈႦ��������c�A�S�����i�T�C�c�v�Ə����Ŗ{�C�Ŏӂ�ޏ��c �����āA��������킹�Ďv�킸���Ă��܂������ɂ��ē�l�ŏ������A����Ȕޏ������āA �u���Ă����q�Ȃ낤�c�B���̎q�Ƃ��t�������������I�v�Ɩ{�C�Ŏv�����B ���̌�A�ޏ��̈ē��ŁA�w�Z�̒��̐F�X�ȃu�[�X�����ĉ�����B ���̍ۂɁA�ޏ�������ŖY����Ȃ��o����������B ����u�[�X�Ő^�ʖڂɁu���v�ɕt���Ĉ������u�[�X���������B �����͏��q�����������A�ޏ������Ȃ�Ɂu���v�ɂ��Đ^���ɍl���A����\����ꂾ�����B ���̃u�[�X�ł͗]��l�C���Ȃ������̂��Ăэ��݂����܂����A��������l�����̑O��ʂ�|���������A�ʂ���ڂ��鐨���Ŏ������𒆂ɓ������Ƃ����B ���̎��A�r����͉��������Ȃ���A�u�S�����i�T�C�I�v�Ə����ŁA���������������āA�Ăэ��݂���}���œ��ꂽ�B ����������ǂ����B �S�z���Ă��鎄�̋C�������@�����̂��A�ޏ��́u���������́A���_���Ȃ́c�v�Ǝ������グ���B ���Ԃ̐_�l�́A��ɕs�������I �܂�Ȃ��Ƃ��͂�����莞�v���A�y�������̓A�b�Ƃ����Ԃɉ߂����点��B �C���t������A�����I���̎��Ԃ������Ă����B �ʂ�鏭���O�ɁA���͂��ꂱ�������̕��䂩���э~���o��Ŕޏ��ɐq�˂��B �u���x�́A��l�ʼn���Ă���܂��H�v �u�͂��c�v �����������悤�Ɏ������グ�A�����Ă͂ɂ��݂Ȃ��ޏ��͌������B ���̏u�ԁA���͐��E��̍K���҂ɂȂ����I�I ���̓��j���A�������͂���R����̉w�ő҂����킹�̖������B |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o� PART-�Q |
�@��T�Ԃ��Ă���Ȃɒ������̂������̂��c�H �悤�₭����ė������̏T���A���͑҂�����̏ꏊ�Ɋ�їE��ŏo�|�����B �҂����킹���Ԃ͊m���ߑO�P�O���A�ꏊ�͉��̂��r����̂i�r�w�@������R����j�w�̃v���b�g�z�[���������B ���̍��̎��̏Z�܂�����A���悻�P���Ԕ��A���͎��Ԃ̗]�T�����ĂQ���ԑO�ɂ͉Ƃ��o���B �j�w�ɂ͑҂����킹�̂R�O���ȏ�O�ɒ������B �x���`�ł������҂��Ă��悤�Ǝv���Ă�����c �r����͂��������Ɉ�l�Ȃ�ł����B �u��������������������c�v �������t���ċ삯���A�ޏ��͏Ƃꂭ�������ɂ����������B �r����Ƃ̂��t�������͖{���Ɋy���������B �������́A���T���̂悤�Ƀf�[�g���d�˂��B �������̃X�k�[�s�[�̃o�b�`���l�Ŕ����A���݂��Ƀv���[���g�������A���݂������Ă���u���U�[�̋��ɕt�����B ����Ȃ��킢�̂Ȃ����Ƃ��A���̍��͖{���ɍK���������B ���x�ڂ̃f�[�g���������낤�c �ޏ��̉Ƃ́A�R����r�܉w����A�o�X�Ő����̏��ɂ������B �f�[�g�̒��ߊ���́A���������r�܉w�̃o�X��܂ő����Ă������B ���̓��A�[���̒r�܉w�͐l���݂ō��ݍ����Ă����B �����Ȕޏ��́A�l�̗���Ɉ��ݍ��܂ꂻ���������B �Ƃ����Ɏ��͔ޏ��Ɏ�������o�����B �����Ĕޏ������߂�킸�Ɏ��̎���������B ���́A�h�L�h�L���Ȃ���A�ޏ���͂ގ�ɏ����͂���ꂽ�B �ޏ�������ɉ�����悤�ɁA���̎������Ԃ��Ă��ꂽ�B ���̎��Ԃ��i���Ɏ~�܂��Ă��܂������Ǝv�����B �ޏ��͂��܂ł����𐩂Łu�s����c�v�ƌĂB ���̕��́u�r�q�����c�v�ƁA�ĂԂ悤�ɂȂ��Ă����B �u�˂��r�q�����A�s����āA���������l�s�V�ŏƂꂭ������B�v �ޏ��͈ӊO�Ȃ��Ƃ�����ꂽ�悤�Ȋ�����Ď��������B �u�x(���̖�)�N�Ƃ������c�v �u�x�E�E�E�N�E�E�E���E�E�E�H�v �ޏ��͏�������悤�Ȑ��Ō������B �炪���錩��Ԃ��Ȃ����B �u���̂ˁA���ꂶ��x����ł������H�v �ޏ��͂��������q�������B�R�̂悤�ɏ���Ȏq�������B ���̎�����ޏ��͎����u�x����c�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B ���v���Ə��Ă��܂����A��قǂ������Ȃ������̂��A�f�[�g�̏ꏊ�͂ǂ��������������������B ��X�،����A�ΐ_������A�P���������A����J�����c �s���̎傾���������ɂ́A�w�Ǎs�����悤�ȋC������B ���Ȃ�A�f�[�g�}�b�v�Ȃǂ��g���Ă����ƋC�̗������ꏊ�ɃG�X�R�[�g����̂��낤���A��������ȃ��m���������Ȃ��A���̎����������ꏊ�Ȃm���Ă���͂����Ȃ������B �ł��A�����Ŏ���q�������Ȃ���A�����ăx���`�ō���Ȃ���b�����邾���ŁA��������Ȃ������B �F�X�Ȃ��Ƃ�b���������B �w�Z�̂��ƁA�F�B�̂��ƁA���̂��ƁA�����Đi�H�̂��Ɓc ����́A�Y������Ȃ��A��̓������������B ���̓��͗₽���J�����Ƃ��ƍ~��A���~�̍��������B �������͂ЂƂ̎P�ŁA�r��n�鋴������Ă����B �r�̃{�[�g����͐l�e���Ȃ��A����������l���w�nj����Ȃ������B ���ꂩ��̐i�w�̘b�����Ă����B �ޏ��̕���͊J�Ǝ��Ȉゾ�����B �����āA�ޏ��͈�l���q�ł������B �ޏ��̕��͔ޏ���������������A�����͎���҂���̂��ł���Ɂc�A�ƁA�ޏ��ɘb���Ă����̂��ƌ����B �ޏ��͍��Z�𑲋Ƃ�����A���ȑ�w���A���ȉq���m�̒Z��ɐi�w����ƌ������B ���͑傢�ɕs���������B �u����ȁA�e�̂����Ȃ�ɃL�~�̐l�����߂��Ⴄ�́H�v �u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�v �u����҂���ƌ����������́H�v �ޏ��͖ق��đ傫��������ɐU�����B �u���Ⴀ���ȑ�Ȃs���Ȃ��ł�I�v �u����Ȃ��Əo���Ȃ��c�v �u���̂����I�H�v �u�����āA�����āA���ꂳ��Ȃ��c�v ���͊��S�ȕ��n�l�ԂŁA���Z�ł͕����n��w�i�w�R�[�X�ɏ������Ă����B �����ȖڂȂA���痚�C���Ă��Ȃ������B ����Ȏ����A���̎��Ƃ����ɍl���Ă����������B �u���ꂶ��A�{�N�����������āA�L�~�Ɠ������ȑ�ɍs����I�@���w�͋�肾���ǁA��P�N�ȏ゠�邵�A�撣���Ă݂��I�@��������L�~�Ɠ�����w�ɍs�����ˁI�H�@���̐l�ƌ����Ȃ��Ȃ��Ă�������ˁI�I�H�v �ޏ��͋����Ď������߂��B �����āA���̑傫�ȓ��������Ǝv���ƁA���ނ����B �嗱�̗܂��A�����������ޏ��̓�����A�ۂƂۂƂƂ��ڂꗎ�����B �ޏ��́A���������������ċ����n�߂��B ���́A�v�킸�������Ă������Ƃ������߂������߂ɔޏ����������̂��Ǝv�����B �u�r�q�����c�v ���́A�S�z�ŁA�ޏ��̌��Ɏ��u�����B ���̏u�ԁA�ޏ��͎��̋��ɂ����݂��Ă����B �����P�������Ȃ���A�Ў�Ŕޏ���������߂��B �u���肢������A�����Ȃ��Łc�B�{�N���������Ȃ����������H�v �ޏ��͋������Ⴍ��Ȃ���A���傫�����ɐU�����B �u���A�Ⴄ�́c�B���c�A�x���c�A�x����D���c�v ���͔ޏ������Ƃ������āA���Ƃ������āA���܂�Ȃ��Ȃ����B �ޏ��𗼎�Ŏv��������������߂��B �����Ă����P�����̎�����A�ӂ��ƕ��ɕ������c ����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��ǂ������c �T���T���Ȕޏ��̒����������̂����т�ɐG��Ă����c �V�����v�[�̊Â����肪�����c �u�r�q�����A�N�𗣂������Ȃ��c�v �����������߂Ȃ��玄�����܂�Ȃ��Ȃ��ęꂭ�ƁA�ޏ��͊���グ�A�G�ꂽ���Ŏ��̖ڂ������c �����āc ���Ԃ��~�܂����c �J�ɑł����܂܂ɁA�������̎��肾���m���Ɏ��Ԃ��~�܂����c |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o� PART-�R |
�@���̓�����r����́A���̐��E���ň�ԑ�Ȑl�ɂȂ����B ���āA���ȑ��ڎw���ɂ͂ǂ�������ǂ��낤�B������w�Z�̃R�[�X��ύX���邱�Ƃ��o����̂��낤���c�B�{�N�ɗ����n�Ȗڂ�������x�ꂩ���蒼���͂�����̂��낤���c�B�S�C�ɑ��k���Ȃ��Ắc�B �ȂǂƐ^���ɔY��ł�����A���̓����琔����A�A��Ă݂�ƈ�ʂ̎莆���|�X�g�̒��ɓ����Ă����B �r���炾�����B�����莆�������B �܂��]�k�ɂȂ邪�A�����������d�b�͂��������A�����������Ǝ莆�ł̂���肪���������B ���̍��́A���ݓ�����O�̂悤�ɁA�e�����ɂP�䂸����q�@�������A���ւ⋏�ԂɂP�䂫��̓d�b�����Ȃ������B ���R�d�b�̘b�����́A�e�Ȃǂ̉Ƒ��ɂ��������������B�����ƉƑ��̎���l�q���C�ɂ��Ȃ���̉�b�ɂȂ邽�߁A�b���h�����ƁA��Ȃ��ƁA���ɗ��l���u�̘A���ɂ́A�ǂ��莆�ŘA������荇�������̂��B �r����Ǝ����A���݂����\����莆�̌����������B �u���̑O�́A�ˑR�������肵�Ă��߂�Ȃ����B�x����̋C�������ƂĂ�������������ł��B�ł��A�������v�ł��B���͎��ȑ�ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��A�x����Ƃ͌����ĕʂꂽ�肵�܂���B�ʁX�̐i�H�ɂȂ��Ă��A�����Ƃx����̂��Ƃ��D���ł��B������A�x����͎����Ō��߂��������ʼn������B���̂��ƂȂŃ}�X�R�~�W�̎d�����������Ƃ����x����̖���ς��Ȃ��Łc�v ����ȓ��e�������B ���͊����������B �u���������Ă��ޏ��ƕʂ�邱�Ƃ͂Ȃ��B�v�u�{�N�B�͂����ƈꏏ�ȂB�v �����M���Ă����c �{�C�ŐM���Ă����c |
| ��Ȃ��̂Ƃ̏o� PART-�S |
�r����Ƃ́A���ꂩ������T���̂悤�Ƀf�[�g���d�˂��B ���̓~�A�A���o���uGARO�R�v�������[�X���ꂽ�B �ޏ��́u�܂͂���Ȃ��v�����C�ɓ��肾�����B���A���͕ʂ�̉̂ł��邻��͕|���čD���ɂȂ�Ȃ������B �ޏ��������̂��A������|�������B �uGARO�R�v�Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ��������B ���ς�炸�A�f�[�g�̏ꏊ�͌��������������B �O�͊����������A��l�ł���Ί����Ȃ�Ċ����Ȃ������B �m���A����J�����֍s�����A�肾�����B �������́A����̃��}�n�y��X�ɍs�����B ���R�[�h������ƂȂ�������A�s�A�m��e������A�����āA�M�^�[�����Ɂc �܂��]�k�����A�����̊y��X�́A��������Ȃ��̂������A���݂����C�y�ɁA�w�ǎ��R�Ɏ��t�����Ă��ꂽ�悤�Ɏv���B ���͓K���Ȉ�{�̃M�^�[���s�b�N�A�b�v���āA�p�ӂ���Ă��鎎�t�p�̈֎q�ɍ������B  �r��������������Ȉ֎q�ɂ������ėׂ�ɍ������B �R�s�[��������́uGARO�R�v�ɓ����Ă��郉�u�\���O�A�u��l�ɂ��Ȃ���v�Ɓu���̌��t�v���M�^�[��e���Ȃ���ޏ��̂��߂����ɉ̂����B ����������ɑ����l�͂������A����Ȃ��Ƃ͓�l�ɂƂ��āc�A���Ȃ��Ƃ����ɂ͑S���C�ɂȂ�Ȃ������B �����ʼn̂��ƍ������o�Ȃ��̂ŁA�u���̌��t�v�͂��Ȃ�傫�ȉ̐��ɂȂ��Ă��܂����B �܂���ɃL�X�����킷�����̊W�̓�l���������A�̎��̈Ӗ������ݒ��߂Ĉꐶ�����̂����B �u���Ă����A�R�Ȃ����ĂȂ����낤�c�@�l�̈��͖{�����c�v �̂��I�������A�ޏ��̓{�N�̌��ɓ����悹�Ă��āA�����₢���B �u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���肪�Ƃ��E�E�E�E�E�E�E�E�E�v �ޏ��͗܂𗬂��Ă����B ��l�̐��E�c ���̎��A�����͓�l�����̐��E�������c |
| LAMB�Ƃ̕ʂ� PART-�P |
�@�V�N���}���A�R�N����ڑO�ɂ��Ď��͂������čQ���������Ȃ��Ă������A�����������o�[�R�l�͕��ی�̋����Ő^���ɘb�����Ă����B �u���ꂩ��ǂ�����c�v �u��������w�ɍs�����I�v �������̊w�Z�́A���̍����猧���L���̐i�w�Z�ŁA�قڂP�O�O������w�ɐi�w���Ă����B �uLAMB�́c�H�v �u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�v  ���v���Ԃ��ƒp���������̂����A���̕����Ղł̃X�e�[�W�ȍ~�A����LAMB�ɂ͎��͂̏��q�Z�𒆐S�Ƀt�@���E�N���u����������Ă����B �������A�S�l�ɂ������Ȃ������ȃN���u���������A�ޏ������̂��߂ɂ����̂܂܂ŏI��炷�̂͐\����Ȃ��C�������F�������Ă����B �ł��A�o���h�Ƃ��Ċ������Ȃ����w���N���A�ł���قNJÂ��͂Ȃ����Ƃ��݂�Ȓm���Ă����B �u���U���邱�Ƃ͎d�����Ȃ����ǁA���̑O�ɉ�����肽���ˁB�v �u����A���U�L�O�̃R���T�[�g��������낤���I�v �u����Ȃ�R���T�[�g�I�I�v �u�������ˁI����Ń{�N�B��������t���Ď��ɐ�O���悤�I�v ���R�ɂȂ钼�O�̍Ō�̏t�x�݂��߂ǂɁA�������́A�uLAMB�[����Ȃ�R���T�[�g�v���J�Â��邱�ƂɌ��߂��B |
| To Be Continued...... |
| �����̃y�[�W�̃g�b�v�ց� |
|
|
SINCE JUNE 16th 1999